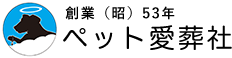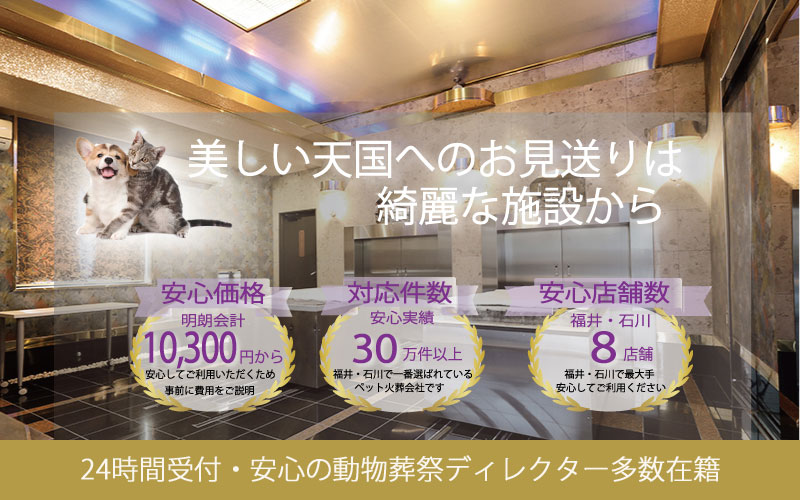1.火葬の歴史
日本では、江戸時代にさかのぼり、人間の火葬は一部上流階級を除き、ほとんどが野焼き同然でした。明治・大正・昭和初期までは各集落などの火葬小屋においてムシロをかけ、炭・石炭・薪などを使用し、10時間程度の時間がかかる原始的な火葬方法がとられてきました。

昭和初期にヨーロッパから日本へバーナー焼却機が入り、現在のような人間の近代火葬は昭和23年に墓地埋葬法が制定されてからで、その後、バーナー焼却機を使用した地方自治体の火葬炉の近代化により、それまでは土葬と同程度の60%程度であった日本の火葬率が徐々に上昇し、昭和55年には9割以上、平成20年においては99.9%と、世界一の火葬率になりました。それに伴い人間と同じ葬送をしたいと想う飼い主の心情もあり、家族動物も土葬から火葬中心の葬送へと変化してきました。その中で昭和28年頃、東京都内の民間動物霊園が火葬炉を設置し火葬をしたのが日本の家族動物の火葬の始まりであり、その後昭和30年代に関東と関西に2、3ヶ所の民間動物霊園による火葬が行われるようになりました。

尚、昭和50年初期に、犬猫等の死体の火葬は一般廃棄物処理に該当するか否かで兵庫県宝塚市と民間動物霊園の間で論争がありましたが、動物愛護先進国であるイギリス大使館の助力もあり、昭和54年、厚生省の担当課長より全国の都道府県廃棄物担当課宛に動物霊園業者等が扱う犬猫等の死体は一般廃棄物とはしないとの内容の通達があり、動物葬儀霊園業者が一般家庭から出た犬猫等の死体の収集・火葬等を業としても一般廃棄物処理業許可は必要ないと行政的に決着し、現在に至っております。



2.火葬及び火葬炉について
火葬または荼毘という行為は、日本国内においては一般的に人体を焼きお骨を収骨する一連の行為を指す言葉ですが、家族動物を家畜ではなく家族と思いお骨を取る為に焼くのであれば、人間以外の動物も火葬と定義する事ができます。
また、ものを焼くという行為には、火葬以外に焼却と加工焼きがあります。焼却とは読んで字の如く焼き去ることであり、その残灰等については意味がなく、一般的に単なる廃棄物として取り扱われることをいいます。またその他には、茶碗を焼くとか金属を焼いて加工するといった、加工的な焼きもあります。
火葬をする炉については色々な形状のものがありますが、お骨を簡単かつ安全に取る事ができる構造のものを火葬炉という事ができます。火葬炉ではなく焼却炉においても、収骨及び骨上げは困難でありますが火葬はできます。ただ、焼却炉ではなく火葬炉と位置付けする為には、単に火葬ができるということだけではなく、収骨及び骨上げが簡単に出来る構造である事が必要です。

3.拾骨の意味と方法
拾骨は骨上げまたは収骨とも表現されます。ヨーロッパでは焼骨を粉状にし骨灰にしますが、日本では遺骨がそのままの形で残るようにします。その意味は、骨に対する日本人の死者に対する思いがあるからです。
日本において、一般的に関東地方とその以北においては、お骨全部を収骨し大きな総骨袋に入れます。また、名古屋地方とその以西においては、全てのお骨ではなく一部のお骨を分骨袋に入れ収骨します。また、骨上げをする時は竹と木で出来た材質の違う二本の箸で拾います。これは「普通ではない」という広い意味があるものと思われます。最初に喪主様が骨を箸で拾い、ご家族など数名が箸から箸へお骨を渡し、最後の人が骨壷へ三回入れる方法が一般的です。
ただし、この収骨および骨上げの方法については、全国いろいろな地域と宗派によって風習が異なり、一概にこれと決めることはできません。極端に言えば、各部落または各町内ごとに風習と慣習が異なる場合もあります。

4.骨上げ及び収骨設備
火葬した後のお骨を取る為、火葬炉内部の火葬床を外部に出す構造としては、レール方式(手動・電動)と台座トレー方式(手動・電動)があります。また、収骨台座の上部はキャスター及びレンガなど耐火材を使用する事が通常ですが、台座にロストルを置き、遺体を浮かせて遺体下部に炎と熱気を入れて火葬しやすくする方式もあります。また最近はキャスタブルの上に高温に耐えられるセラミックファイバーを敷き置く事も多くなりました。その他一部には、特殊な砂をキャスタブルの上に敷きキャスタブルの劣化を防ぐ構造の物もあります。
火葬後に火葬床をレールに沿って火葬炉外部に出し収骨をする方式が、最近の動物火葬炉として一番多い構造方式となります。又鉄板などを台座に使用し、火葬床を外部に直接排出する方式もありますが、この方法は台座の金属については耐久性に問題があります。台座トレー方式は、火葬後に台座をトレーとして火葬炉の外部に火葬床を出し、台座トレーを別の部屋などへ移動し収骨します。
また火葬場の建物の構造として、火葬炉本体を置く部屋と収骨をする部屋が分かれているものと、炉本体を置く部屋と収骨室が同じものがあります。心情的に喪主様の意識は家族動物も人間同様であり、各自治体の人間の火葬場の構造が炉室と収骨室が別々であることが圧倒的に多いので、一般的には家族動物の喪主様も、火葬炉室と収骨室の分離型を好まれる傾向があります。

5.火葬燃焼器の種類
燃焼器の燃料については、重油、灯油に対応する物と、プロパン、都市ガスなどガスを使用する物とがあります。重油は価格が安く温度も上がりやすい利点がありますが、灯油に比べて煤煙等が発生する事が多い為、灯油を使用する場合が圧倒的に多くなっています。またプロパンなどガスについては、煤煙及び温度等については優れた面もありますが、万一ガス漏れなどが発生しても見た目には発見しづらい面があります。但し最近はガス警報器を使用し、ガス漏れがあっても自動的に燃焼を停止する構造なので、危険性はほとんど無いと思われます。
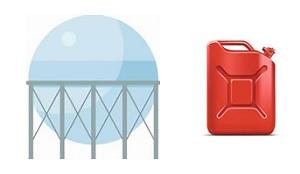
しかし燃料の違いは燃焼器にとっては大きな問題ではなく、火葬能力、環境公害、収骨機能性、優美性、燃費、価格等について考え選択する事が必要です。
またバーナーの種類は、ガンタイプバーナー(オイル、ガス焚)、ロータリーバーナー(回転式)、高圧スプレーバーナー、低圧スプレーバーナーなどがあります。バーナーは基本的にはオイルポンプより圧力をかけた油をノズル口より霧状に噴射し、そのノズルの先に高圧電流の火花を散らし着火し燃焼する方式となっております。ガスの場合は圧力のかかったガスがノズルより噴射し、高圧電流の火花により着火し燃焼します。また、ガンタイプの場合、噴射ノズルが二つ装着のバーナーもあります。また燃料をできるだけ前方に通し炎を全面に押し出す為、ファンの回転による風圧式と、圧縮空気による圧力式による噴射などがあります。
6.煙突等の空気循環装置
焼く事とは、焼く対象と空気中に含まれる酸素との温度変化による化学反応ですので、空気循環は非常に大事な事です。一般的に自然空気循環型としての煙突は、高さイコール吸引力であり、煙突の太さイコール吸引量となります。また強制空気循環としては、ファン回転式による空気の直接排気と、煙突内の圧縮空気噴射によって強制的な空気の流れを作るエジェクター方式の間接強制排気があります。又、火葬炉がある建物部分には煙突など排出口と同じ大きさの空気取入口を作り、炉への充分な空気(酸素)注入を行う事が必要です。


7.火葬の安全な作業
動物の火葬業務においては炉の温度が非常に高温の為まず火傷が心配されますが、それ以上に危険な要素として、数百キロもの重さの扉等の落下や、火葬時のお棺内の温度差による炉内の爆発可能物の爆発や、炉内の耐火材の水蒸気爆発などが考えられます。
火傷事故については、バーナーの焼却を止めた後冷却時間を充分取るなどすれば回避できます。

また、お棺内の温度差による爆発物については、火葬前に火葬床上の危険物を除去する事と火葬中の炉内の確認窓からの目視の時に特に気を付ける事が重要です。火葬し終わった後は、もし爆発可能物があったとしても爆発は終わっており、収骨の時に爆発する事はほとんどありません。
また、低セメント系キャスタブルで構築された炉で炉内の張り替え等を行った後に、最初に使用する時は水分が残っていると水素爆発を生じ、轟音と共にキャスタブルが吹き飛ぶ事があるので、最初の使用時の温度上昇には注意が必要です。
その他、火葬炉の周りはいつも整理整頓をし、火葬時の事故防止に努める事が大切です。


動物葬祭ディレクター1級 中村
福井動物霊苑
910-0818 福井県福井市堂島町110 0776-54-5073
ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂
サンドーム北動物霊苑
916-0042 福井県鯖江市新横江1-816 0778-54-0005
ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂
大安寺動物霊苑
910-0044 福井市田ノ谷町(大安禅寺敷地内)0776-59-1760
ペット納骨堂 ペット霊苑
セレモニープラザあわら
919-0737 あわら市権世 0776-74-1182
動物火葬場 ペット火葬場 ペット霊園
石川店
西部緑地動物霊苑 ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂
小松ペット霊園 ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂
金沢寺町動物霊苑 ペットセレモニー室 ペット納骨堂
セレモニー森本 ペット火葬場 動物火葬場